遺言について(自筆証書遺言)
遺言を利用すれば、生前のうちに、誰にどのような財産を残しておくのか、決めておくことができます。
さらには、遺言を残しておけば、相続人間での争いを予防させることができ、もはや遺言を残しておくことは生前の義務と考える見方もあります。
なお、遺言は法律に従った用件を備えていなければ無効になりますし、内容の書き方によっては、思いどおりの結果にならないことがあります。
遺言は生前の最後の意志表示ですので、間違いがないように、確かなものを残しておくことが必要です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、自分が全文を自筆して作成する遺言のことです。
代わりに代筆してもらうと無効になりますので、病気などで字が書けない方は作成することができません。
また、せっかく作成した遺言が紛失や焼失した場合も遺言書が無効なりますので、保管にも注意が必要です。
一方で、公正証書遺言(公証人に作成してもらう遺言)とは異なり、公証人など第三者に確認してもらう必要がなく、簡易に作成することができますし、公証人への手数料も不要となります。
なお、実際に遺言書を利用する際は、家庭裁判所への「検認」をする必要があります。
司法書士の役割はなに?
自筆証書遺言の場合、遺言者が自分で簡易に作成することができるといっても、せっかく作成した遺言が無効であったり、思いどおりの結果にならないものであれば、全く無意味なものです。
また、公正証書遺言と異なり作成途中に公証人(第三者)の関与が全くないのも不安点と考えられる方もいらっしゃるでしょう。
司法書士は、遺言者の現状や希望を聞き取ったり、現在の財産状況を確認するなどし、どのような遺言内容にすべきかを、遺言者と一緒に決めていきます。また、完成した遺言書をチェックして、遺言書の形式に不備がないかを確認し、さらに希望であれば遺言書の原本や写しを保管することもお受けしております。
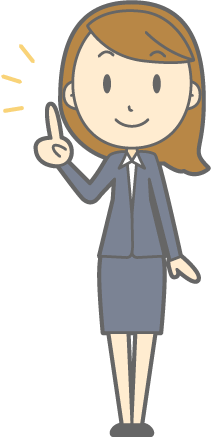
お手続き完了までの流れ
ご相談内容をお伺いし、どの方法で遺言を作成するか検討します。
また、ご相談内容によっては、遺言ではなく生前贈与を利用した方が良い場合もありますので、合わせて検討します。
遺言の内容を具体的に検討します。既に遺言内容を決定されている場合は、抜け落ちている点がないか、実際に思いどおりの内容が実現できるかなど検討します。
当事務所で遺言の文案をご用意します。
文案を見て頂き、御自身のお考えと食い違う点がないか、最終確認を 行います。
事務所や自宅などで執筆をして頂きます。お手続の費用は、最後に清算いたします。
見積に必要な書類
※見積もりに必要な書類はありませんが事案内容の聞き取りをします。
手続きに必要な書類
○ ……ご本人にご用意していただく書類
△ ……ご本人もしくは、当社でご用意可能な書類
| ○ | 免許証又は保険証など本人確認書類 |
料金表
| 費用 | 費用 |
|---|---|
| 実費 | 戸籍代、登記簿代など |
| 報酬 | 1人当たり6万円~10万円(税別) |
※上記はあくまで一例であり、お客様の状況により異なることがございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
